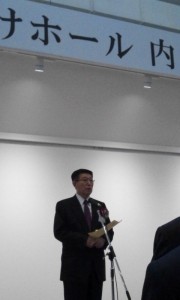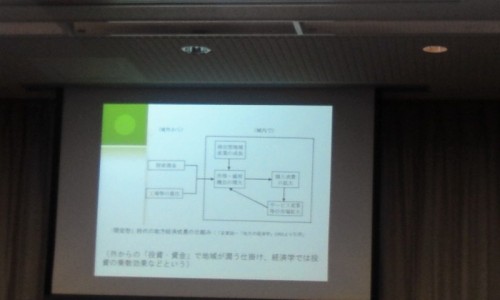政治家の新春懇談会が秋田市中心の集まりから地方にかけて盛んと行われている。
政治の世界はこうした機会に多くの方々と知り合いになり、情報交換をし、次の機会に抱える課題についての考え方や、運動の仕方などの情報を得ておいて、活動する機会にもなる。
実際、今年みたいな豪雪の年については、雪害対策、除雪費用の増大対策の財源対策、さらには特別交付税対策など広範にわたりその情報をもらわなければならない。
そうした意味合いからすれば、新春懇談会だけではない「新春懇談会」の意味合いが出てくる。
どこをどう押せばよいのか、どんな方々の意見が通りやすいかなど、人と人の付き合い、関係の深さなどを十分に知る必要性もあり、それらが複雑に絡んでくるからややこしい。
しかし、それをうまく結びつけるのもこうした機会になることになるのでしょう。
昨日の会合でも、これまで知らなかった人間関係を深く知る機会となりとても参考になった。
これからもまだまだこうした機会があり、そうした視点での懇談を重ねていきたいと感じたところでした。
今朝の山里は霧がかかった朝で、夜明けも遅かった。
政治家の新春懇談会が秋田市中心の集まりから地方にかけて盛んと行われている。
政治の世界はこうした機会に多くの方々と知り合いになり、情報交換をし、次の機会に抱える課題についての考え方や、運動の仕方などの情報を得ておいて、活動する機会にもなる。
実際、今年みたいな豪雪の年については、雪害対策、除雪費用の増大対策の財源対策、さらには特別交付税対策など広範にわたりその情報をもらわなければならない。
そうした意味合いからすれば、新春懇談会だけではない「新春懇談会」の意味合いが出てくる。
どこをどう押せばよいのか、どんな方々の意見が通りやすいかなど、人と人の付き合い、関係の深さなどを十分に知る必要性もあり、それらが複雑に絡んでくるからややこしい。
しかし、それをうまく結びつけるのもこうした機会になることになるのでしょう。
昨日の会合でも、これまで知らなかった人間関係を深く知る機会となりとても参考になった。
これからもまだまだこうした機会があり、そうした視点での懇談を重ねていきたいと感じたところでした。
今朝の山里は霧がかかった朝で、夜明けも遅かった。 新春懇談会
 政治家の新春懇談会が秋田市中心の集まりから地方にかけて盛んと行われている。
政治の世界はこうした機会に多くの方々と知り合いになり、情報交換をし、次の機会に抱える課題についての考え方や、運動の仕方などの情報を得ておいて、活動する機会にもなる。
実際、今年みたいな豪雪の年については、雪害対策、除雪費用の増大対策の財源対策、さらには特別交付税対策など広範にわたりその情報をもらわなければならない。
そうした意味合いからすれば、新春懇談会だけではない「新春懇談会」の意味合いが出てくる。
どこをどう押せばよいのか、どんな方々の意見が通りやすいかなど、人と人の付き合い、関係の深さなどを十分に知る必要性もあり、それらが複雑に絡んでくるからややこしい。
しかし、それをうまく結びつけるのもこうした機会になることになるのでしょう。
昨日の会合でも、これまで知らなかった人間関係を深く知る機会となりとても参考になった。
これからもまだまだこうした機会があり、そうした視点での懇談を重ねていきたいと感じたところでした。
今朝の山里は霧がかかった朝で、夜明けも遅かった。
政治家の新春懇談会が秋田市中心の集まりから地方にかけて盛んと行われている。
政治の世界はこうした機会に多くの方々と知り合いになり、情報交換をし、次の機会に抱える課題についての考え方や、運動の仕方などの情報を得ておいて、活動する機会にもなる。
実際、今年みたいな豪雪の年については、雪害対策、除雪費用の増大対策の財源対策、さらには特別交付税対策など広範にわたりその情報をもらわなければならない。
そうした意味合いからすれば、新春懇談会だけではない「新春懇談会」の意味合いが出てくる。
どこをどう押せばよいのか、どんな方々の意見が通りやすいかなど、人と人の付き合い、関係の深さなどを十分に知る必要性もあり、それらが複雑に絡んでくるからややこしい。
しかし、それをうまく結びつけるのもこうした機会になることになるのでしょう。
昨日の会合でも、これまで知らなかった人間関係を深く知る機会となりとても参考になった。
これからもまだまだこうした機会があり、そうした視点での懇談を重ねていきたいと感じたところでした。
今朝の山里は霧がかかった朝で、夜明けも遅かった。