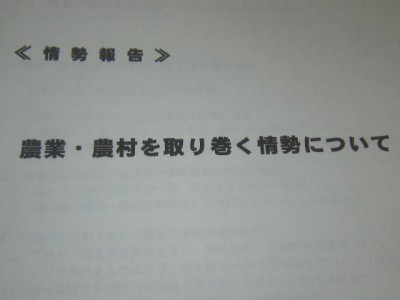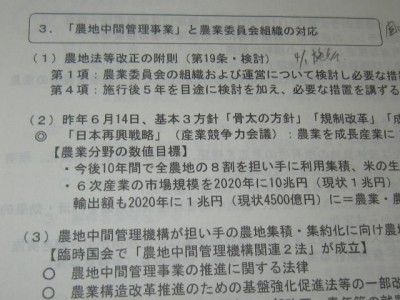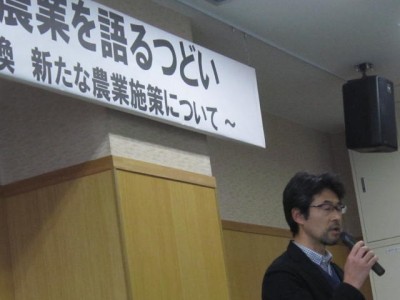(今朝の冬空の雲に孫が関心を示し、朝焼けの焼石連峰です)
続くときは続くもので「国土強靭化対策」の講演を2週連続してお聞きすることになった。
先週は全国町村会の会議での研修、今回は銀行の会員総会での講演で講師は、同じ藤井聡氏でした。
さすがに2回目とあって今回はかなり理解度が深まった。
前段は、経済学の問題、メデイアの国土強靭化に対する報道が単なるばらまきと政策いう批判に猛烈に反論しており、経済のトリクロ理論の危うさに鋭くメスを入れ、景気の悪い時、デフレ経済からの脱却には、公共事業の投資が絶対に必要である。
これは、好況時には民間資本が積極的に自社の投資を進めることからそんな対応策は必要ないが、不況時には国、地方公共団体などの公共機関が積極的に投資を押し進める施策が求められる。
その対象は、近くに予想される東海地震を中心にした、東海、首都圏の防災対策などは3・11を大幅にしのぐ投資が必要であり、道路交通、鉄道などその範囲は限りなく大きな投資が求められる。
同時に、その対策は国土全体に及ぶことになる、そのための施策がこれから具体的に安倍政権によって示されることになる。
そのための協議が政府機関において精力的に進められているようである。
昨日は、朝早くから、村の社旗福祉協議会の理事会、評議員会を開催し補正予算や要綱の改正など審議し決定、そのあとこの講演会に出て、懇親会後、村での農事組合法人の新年祝賀会での意見交換会と結構盛りだくさんの日程をこなした。
この法人は、若い世代の法人で、野菜、シイタケ、水耕栽培、ユリ栽培など新たな取り組みをする法人で、未経験ながらぜひ頑張ってほしい法人で我々も積極的に支援したい団体である。


 このところお天気も落ち着いてゆっくりさせてもらっている。
公共施設、特に保育園、小学校の駐車場の排雪を村の建設業協会のご協力で計画的に進めてもらっている。
特に、保育園は保護者が送迎しており、その車の駐車スペース、回転などに相当苦労しておられたようですが、今回いろいろな国、県のご協力もあり広いスペースが確保でき大変有り難かった。
この後岩井川の交流施設ゆるるん、もしもしピットなど主要施設でも順次排雪が進めば、より安心した対策が取られることになります。
このあと何とか天気が落ち着いてくれればばと願わすにはおられません。
2月にはもう一度寒波の襲来があるようですが、穏やかであって欲しいものです。
このところお天気も落ち着いてゆっくりさせてもらっている。
公共施設、特に保育園、小学校の駐車場の排雪を村の建設業協会のご協力で計画的に進めてもらっている。
特に、保育園は保護者が送迎しており、その車の駐車スペース、回転などに相当苦労しておられたようですが、今回いろいろな国、県のご協力もあり広いスペースが確保でき大変有り難かった。
この後岩井川の交流施設ゆるるん、もしもしピットなど主要施設でも順次排雪が進めば、より安心した対策が取られることになります。
このあと何とか天気が落ち着いてくれればばと願わすにはおられません。
2月にはもう一度寒波の襲来があるようですが、穏やかであって欲しいものです。