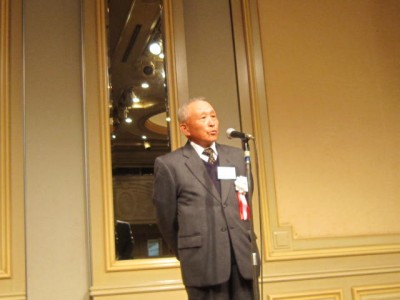成瀬会を終えて、ホテルから帰路に就く。
都内、特に泊まったホテル周辺は閑散としていた。
こういうときに忙しいのは、高層ビルなどの窓掃除点検でしょう。
あんな高い所からロープ二本でぶら下がり、しっかりと手早く作業中!次々と移動、こんな方々の作業賃金も高いだろうなー!なんて、詰まらない事を考えてパチり。
三連休の最後、乗り物は結構混んでいました。
成瀬会に参加してくれた方々からメールもどんどん入っていました。
参加すると、いろんな方と会えるし、話すことができてすごく楽しいとのこと。同級生とも会えてとっても良かった!
こんな形で広がりを見せてくれると嬉しい限りです。
特に、段階の世代の方々にそうした動きがあり、期待したい。
成瀬会を終えて、ホテルから帰路に就く。
都内、特に泊まったホテル周辺は閑散としていた。
こういうときに忙しいのは、高層ビルなどの窓掃除点検でしょう。
あんな高い所からロープ二本でぶら下がり、しっかりと手早く作業中!次々と移動、こんな方々の作業賃金も高いだろうなー!なんて、詰まらない事を考えてパチり。
三連休の最後、乗り物は結構混んでいました。
成瀬会に参加してくれた方々からメールもどんどん入っていました。
参加すると、いろんな方と会えるし、話すことができてすごく楽しいとのこと。同級生とも会えてとっても良かった!
こんな形で広がりを見せてくれると嬉しい限りです。
特に、段階の世代の方々にそうした動きがあり、期待したい。 休日の都内は閑散
 成瀬会を終えて、ホテルから帰路に就く。
都内、特に泊まったホテル周辺は閑散としていた。
こういうときに忙しいのは、高層ビルなどの窓掃除点検でしょう。
あんな高い所からロープ二本でぶら下がり、しっかりと手早く作業中!次々と移動、こんな方々の作業賃金も高いだろうなー!なんて、詰まらない事を考えてパチり。
三連休の最後、乗り物は結構混んでいました。
成瀬会に参加してくれた方々からメールもどんどん入っていました。
参加すると、いろんな方と会えるし、話すことができてすごく楽しいとのこと。同級生とも会えてとっても良かった!
こんな形で広がりを見せてくれると嬉しい限りです。
特に、段階の世代の方々にそうした動きがあり、期待したい。
成瀬会を終えて、ホテルから帰路に就く。
都内、特に泊まったホテル周辺は閑散としていた。
こういうときに忙しいのは、高層ビルなどの窓掃除点検でしょう。
あんな高い所からロープ二本でぶら下がり、しっかりと手早く作業中!次々と移動、こんな方々の作業賃金も高いだろうなー!なんて、詰まらない事を考えてパチり。
三連休の最後、乗り物は結構混んでいました。
成瀬会に参加してくれた方々からメールもどんどん入っていました。
参加すると、いろんな方と会えるし、話すことができてすごく楽しいとのこと。同級生とも会えてとっても良かった!
こんな形で広がりを見せてくれると嬉しい限りです。
特に、段階の世代の方々にそうした動きがあり、期待したい。