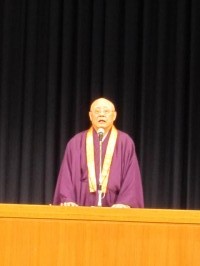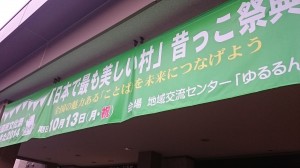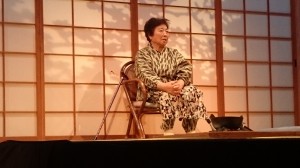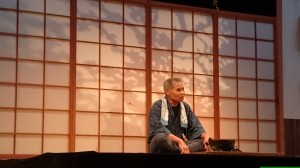松島にある藤田喬平美術館を初めて観覧。
その不思議な彩りに時間を忘れて見とれてしまった。
作品の制作状況もビデオ鑑賞したが、大変な工程を、ガラス職人と共に完成させる一体感は他の芸術にもあるのだろうか?
長男の作品も展示されており、親子での工芸作家は珍しいのかなとも感じた。
所々にある藤田喬平語録はユウモアに溢れ、とても読み応えのあるものでした。
そのあと、一度みたいと思っていた仙台の光のページエントの点灯の瞬間を見に行った。
生憎の小雨模様であったが、点灯の瞬間の一斉に上がった歓声ともどよめきとも言える雰囲気はさすがであった。
始まった頃よりは、景気の影響もあり、規模はかなり小さくなったとのこと。
それでも始めてみる私からすると規模はさすがに、大きいものでした。
仙台であっても復興景気とか言われてはいるが、こうしたイベントに対する寄付金も少ないということは、景気がここであっても及んでいないことの証左であることょうか?
松島にある藤田喬平美術館を初めて観覧。
その不思議な彩りに時間を忘れて見とれてしまった。
作品の制作状況もビデオ鑑賞したが、大変な工程を、ガラス職人と共に完成させる一体感は他の芸術にもあるのだろうか?
長男の作品も展示されており、親子での工芸作家は珍しいのかなとも感じた。
所々にある藤田喬平語録はユウモアに溢れ、とても読み応えのあるものでした。
そのあと、一度みたいと思っていた仙台の光のページエントの点灯の瞬間を見に行った。
生憎の小雨模様であったが、点灯の瞬間の一斉に上がった歓声ともどよめきとも言える雰囲気はさすがであった。
始まった頃よりは、景気の影響もあり、規模はかなり小さくなったとのこと。
それでも始めてみる私からすると規模はさすがに、大きいものでした。
仙台であっても復興景気とか言われてはいるが、こうしたイベントに対する寄付金も少ないということは、景気がここであっても及んでいないことの証左であることょうか?