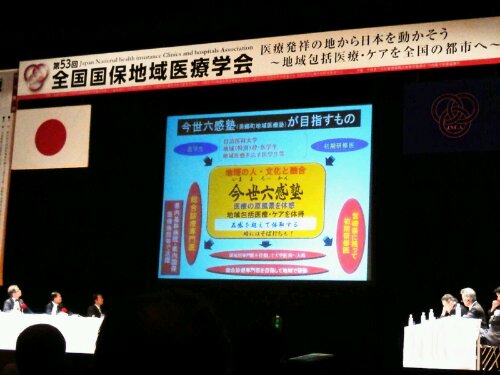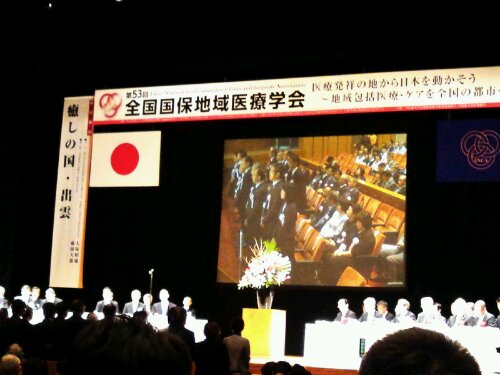隠岐の海士町と西の島町を訪問している。
鳥取県七類港から フェリーで約3時間あまり途中知夫村の来去港、西ノ島町の別府港、海士町の菱浦港などに寄港しての航路である。
海士町では山内町長さんと離島振興、キャッチコピー「ないものはない」の趣旨、町おこしなどを、斎藤会長とご一緒に意見交換させて頂いた。昨日まで日本で最も美しい村連合の戦略会議が開かれており、最終日で出席した方々を見送りされていた、大変忙しい合間の町長さんに面接できて、恐縮した。
海士町にその手伝いを兼ねてきていた、地域おこし協力隊の佐藤さんの案内で町内を視察させて頂いた。
先日、魁新報のシリーズもので紹介された、海士町在住の秋田県出身の秋元さんと町営学習塾の話しができて、とても参考になり、今後の方向付けにもなった。
民家を借りての塾であり、間もなく、別建ての施設が計画されているとのことでもあった。
何よりも、この離島で秋田県出身者が頑張っていることに感激もした。
200人を超える移住者がいること、その多くが、教育などのための移住であること、そのきっかけ、今後にかなりの関心を持つこととなった。
それは秋元さんを含む指導者であり、勉強、受験生であることにも
強い関心を持ったところでした。
隠岐諸島は多くの島で構成されていた、歴史的にも古く、海路の重要港湾があり、後鳥羽上皇や後醍醐天皇などの遠流の地でもあり、政治に関わって流された著名人も多かった歴史の地域でもある。
直木賞作家・安部龍太朗さんの「天馬翔ける」の最後の場面で、天馬密輸の輸送中に、嵐に遭遇、避難した港はどこだったのか?船から下ろし疾走させた草原はどこだったのか?西ノ島の鬼舞展望か国賀の魔天崖の地であっただろうか?最終目的地の境港に無事つき、運んできた「天馬」を幕府に献上したロマンあふれる小説を思い出した。
そうした尽きない想像が次々と浮かんでくる、要衝の地の隠岐であった。
海士町は小綺麗な掃除の行き届いた、街で、気配りのある町とみた。
公共施設もさりげなく掃除が行き届いていた。
隠岐の海士町と西の島町を訪問している。
鳥取県七類港から フェリーで約3時間あまり途中知夫村の来去港、西ノ島町の別府港、海士町の菱浦港などに寄港しての航路である。
海士町では山内町長さんと離島振興、キャッチコピー「ないものはない」の趣旨、町おこしなどを、斎藤会長とご一緒に意見交換させて頂いた。昨日まで日本で最も美しい村連合の戦略会議が開かれており、最終日で出席した方々を見送りされていた、大変忙しい合間の町長さんに面接できて、恐縮した。
海士町にその手伝いを兼ねてきていた、地域おこし協力隊の佐藤さんの案内で町内を視察させて頂いた。
先日、魁新報のシリーズもので紹介された、海士町在住の秋田県出身の秋元さんと町営学習塾の話しができて、とても参考になり、今後の方向付けにもなった。
民家を借りての塾であり、間もなく、別建ての施設が計画されているとのことでもあった。
何よりも、この離島で秋田県出身者が頑張っていることに感激もした。
200人を超える移住者がいること、その多くが、教育などのための移住であること、そのきっかけ、今後にかなりの関心を持つこととなった。
それは秋元さんを含む指導者であり、勉強、受験生であることにも
強い関心を持ったところでした。
隠岐諸島は多くの島で構成されていた、歴史的にも古く、海路の重要港湾があり、後鳥羽上皇や後醍醐天皇などの遠流の地でもあり、政治に関わって流された著名人も多かった歴史の地域でもある。
直木賞作家・安部龍太朗さんの「天馬翔ける」の最後の場面で、天馬密輸の輸送中に、嵐に遭遇、避難した港はどこだったのか?船から下ろし疾走させた草原はどこだったのか?西ノ島の鬼舞展望か国賀の魔天崖の地であっただろうか?最終目的地の境港に無事つき、運んできた「天馬」を幕府に献上したロマンあふれる小説を思い出した。
そうした尽きない想像が次々と浮かんでくる、要衝の地の隠岐であった。
海士町は小綺麗な掃除の行き届いた、街で、気配りのある町とみた。
公共施設もさりげなく掃除が行き届いていた。