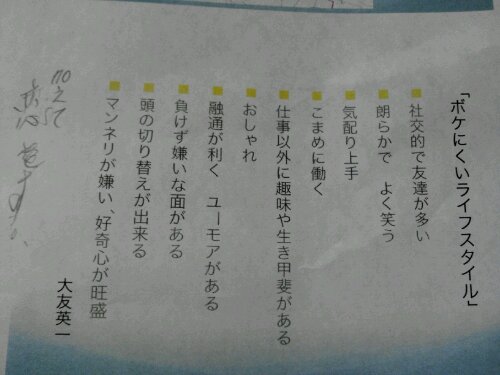国家公務員の給与を7・8%引き下げすることにより地方公務員との給与に差額が生じ、均衡が取れないとして、国では地方公務員の給与を引き下げるような通達を出した。
すでに、メデイアで昨年あたりから盛んに報道されているのであるが、どうも納得がいかない。
この比較に当たっては「ラスパイレス指数」という手法で国家公務員と地方公務員の給与を5歳刻みで比較することがこれまでなされてきた。
この比較では、一般的に地方公務員が一部の地方自治体を除いて国家公務員よりも、この指数で100を割り込むのが通例で、地方が低くなっていた。
つまり、この指数100よりも低く抑えられていた。たとえばわが村の場合は低いときには80台であったり、最近でも90台であったし、常に国よりは相当低くなっていた。しかも、国では地域手当とか調整手当とかと称する手当が恒常的に毎月手当として支給されているようであるが実態はわかりません。いずれ、この手当部分は比較対象にはなっておらないようである。実質的な手取り額ではかなりの開きがあるようであるが実際はわかりません。
一方でこれまで高い給与のままで来ていたのに、復興財源にするために一時的に国家公務員給与を引き下げたのであるから、地方はこれまで低いままの給与であったのに、一時的に比較して高くなったから引き下げしなさいということになることにどこか納得がいかないし、腑に落ちないことが正直な気持ちである。
また、地方の給与であっても、県の職員、大きな市の職員、特別市の市職員など、地方公務員といってもそうした団体とわが村の職員と一緒にしても無理があり、そうした地方公務員と国家公務員との比較でよいのかといった議論も必要なような気がしてならない。つまり、その「地方公務員」についてもかなりのばらつきがあることも事実であるように思っているが違うのであろうか?
今回わが村の場合、すでに新聞などで報道されているが、国を100とした場合に103・5という数値が報道された。
これは、言いわけでもなんでもないが、行財政改革を進めてきている中で、退職者を補充せずに、懸命に行財政改革を進め、経費の節減に努め、やっとここまで来たのに、今度は給与を削減するようにとなっては、ダブルパンチもよいところであり、困惑しきっている。
新規の職員採用も極力抑え、民間委託できるところは委託をして頑張ってきたし、改革プランでも平成24年現在、一般職員で基準年の平成17年に比較し44名から31名になっている。教育関係職員では、6名から5名になり、企業会計では51名から32名の実職員数となっている、総体では67・3%の削減率である。
当然、新規採用が少なく、職員の年齢構成が高くなってきているのも事実であるし、それだけに給与も高くなっていることも事実であるが、5歳刻みの枠の中にどれだけの人員がいるのか、大きな自治体と小さな自治体では職員数もかなりの開きがあるので、比較するには無理があるような気がする。しかし、このラスパイレス指数はこれまで比較指数としてしっかり定着してきているもので、簡単にはこの指数には太刀打ちできないのが現状の様な気もする。
いずれ、国では地方の行財政改革に取り組んだそうした努力も反映させると言っているようであるが、まだ具体的にはそうした指示はないようである。
この指示指導に対しては、国ではすでに地方交付税を4千億円を削減する予算を組んでおるようであり、ラスパイレス指数比較で100を超えている団体はこの交付税で削減対象にならざるを得ない状況であるようである。
困ったことである。
国では、そうした職員削減をしたのであろうか、そうした削減をどのようにおこなったのであろうか。
そもそもこの比較のし方にも、町村によっては職員採用の時期や、改革プランの実行過程、5歳刻みの比較のし方、在籍者の年齢構成、その年によって大きく変動しますし、その自治体の事情にもよるわけであり、何万人もおる国家公務員とごく数人しかおらない職員との比較は適切かどうかもあるように思えるのですがどうであろうか?
いずれ、こうした改革の実施状況をどう判断するかが今後大きくこの対策に関わってくるものと思えるし、これに期待したいと思っている。
秋田県内の自治体でも相当苦慮することになりそうである。
そとは青空、冬空にこの青空は、そんなうっ屈した空気を少しでも和らげてくれてありがたい。
でも週末はまたまた荒れてきそうであるが、春はもうそこまで来ていることでしょう!
前向きに考えて進んでいきたいものです。
国家公務員の給与を7・8%引き下げすることにより地方公務員との給与に差額が生じ、均衡が取れないとして、国では地方公務員の給与を引き下げるような通達を出した。
すでに、メデイアで昨年あたりから盛んに報道されているのであるが、どうも納得がいかない。
この比較に当たっては「ラスパイレス指数」という手法で国家公務員と地方公務員の給与を5歳刻みで比較することがこれまでなされてきた。
この比較では、一般的に地方公務員が一部の地方自治体を除いて国家公務員よりも、この指数で100を割り込むのが通例で、地方が低くなっていた。
つまり、この指数100よりも低く抑えられていた。たとえばわが村の場合は低いときには80台であったり、最近でも90台であったし、常に国よりは相当低くなっていた。しかも、国では地域手当とか調整手当とかと称する手当が恒常的に毎月手当として支給されているようであるが実態はわかりません。いずれ、この手当部分は比較対象にはなっておらないようである。実質的な手取り額ではかなりの開きがあるようであるが実際はわかりません。
一方でこれまで高い給与のままで来ていたのに、復興財源にするために一時的に国家公務員給与を引き下げたのであるから、地方はこれまで低いままの給与であったのに、一時的に比較して高くなったから引き下げしなさいということになることにどこか納得がいかないし、腑に落ちないことが正直な気持ちである。
また、地方の給与であっても、県の職員、大きな市の職員、特別市の市職員など、地方公務員といってもそうした団体とわが村の職員と一緒にしても無理があり、そうした地方公務員と国家公務員との比較でよいのかといった議論も必要なような気がしてならない。つまり、その「地方公務員」についてもかなりのばらつきがあることも事実であるように思っているが違うのであろうか?
今回わが村の場合、すでに新聞などで報道されているが、国を100とした場合に103・5という数値が報道された。
これは、言いわけでもなんでもないが、行財政改革を進めてきている中で、退職者を補充せずに、懸命に行財政改革を進め、経費の節減に努め、やっとここまで来たのに、今度は給与を削減するようにとなっては、ダブルパンチもよいところであり、困惑しきっている。
新規の職員採用も極力抑え、民間委託できるところは委託をして頑張ってきたし、改革プランでも平成24年現在、一般職員で基準年の平成17年に比較し44名から31名になっている。教育関係職員では、6名から5名になり、企業会計では51名から32名の実職員数となっている、総体では67・3%の削減率である。
当然、新規採用が少なく、職員の年齢構成が高くなってきているのも事実であるし、それだけに給与も高くなっていることも事実であるが、5歳刻みの枠の中にどれだけの人員がいるのか、大きな自治体と小さな自治体では職員数もかなりの開きがあるので、比較するには無理があるような気がする。しかし、このラスパイレス指数はこれまで比較指数としてしっかり定着してきているもので、簡単にはこの指数には太刀打ちできないのが現状の様な気もする。
いずれ、国では地方の行財政改革に取り組んだそうした努力も反映させると言っているようであるが、まだ具体的にはそうした指示はないようである。
この指示指導に対しては、国ではすでに地方交付税を4千億円を削減する予算を組んでおるようであり、ラスパイレス指数比較で100を超えている団体はこの交付税で削減対象にならざるを得ない状況であるようである。
困ったことである。
国では、そうした職員削減をしたのであろうか、そうした削減をどのようにおこなったのであろうか。
そもそもこの比較のし方にも、町村によっては職員採用の時期や、改革プランの実行過程、5歳刻みの比較のし方、在籍者の年齢構成、その年によって大きく変動しますし、その自治体の事情にもよるわけであり、何万人もおる国家公務員とごく数人しかおらない職員との比較は適切かどうかもあるように思えるのですがどうであろうか?
いずれ、こうした改革の実施状況をどう判断するかが今後大きくこの対策に関わってくるものと思えるし、これに期待したいと思っている。
秋田県内の自治体でも相当苦慮することになりそうである。
そとは青空、冬空にこの青空は、そんなうっ屈した空気を少しでも和らげてくれてありがたい。
でも週末はまたまた荒れてきそうであるが、春はもうそこまで来ていることでしょう!
前向きに考えて進んでいきたいものです。