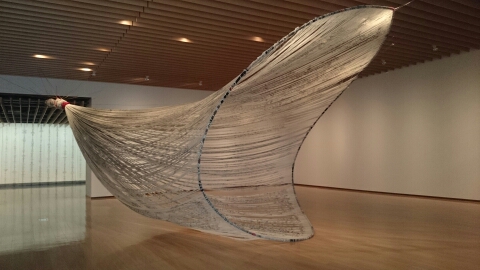(開会式)
(開会式)
 (スコアボードにみいる選手たち)
(スコアボードにみいる選手たち)
 (閉会式前の談笑)
第4回目になる東北パークゴルフ選手権大会が行われ、開会式で挨拶をさせていただいた。
デンバーから帰って直ぐに、九州での行政視察と体調の維持にはかなり苦労したように思っている。
日常的には大して変わった生活をしていないように感じても、からだの内部では、相当異常だったんではないだろうか。
どこかスッキリしない。
体内時計は間違いなく、異常になっていたのでしょう。
昨日の夕方、つい横になって休んだところ、ぐっすりと寝てしまい、そうしたらスッキリした。
パークゴルフ大会は、203名の参加で、東北全体からの出場。
それぞれ相当自信満々の選手たちばかりで、レベルも相当高い大会となって来ている。
天候が雨模様で選手は相当苦労したようであった。
優勝は男女とも奥州市の選手であった。
これから、仙北道の踏査隊の歓迎会があり、これに出席します。
(閉会式前の談笑)
第4回目になる東北パークゴルフ選手権大会が行われ、開会式で挨拶をさせていただいた。
デンバーから帰って直ぐに、九州での行政視察と体調の維持にはかなり苦労したように思っている。
日常的には大して変わった生活をしていないように感じても、からだの内部では、相当異常だったんではないだろうか。
どこかスッキリしない。
体内時計は間違いなく、異常になっていたのでしょう。
昨日の夕方、つい横になって休んだところ、ぐっすりと寝てしまい、そうしたらスッキリした。
パークゴルフ大会は、203名の参加で、東北全体からの出場。
それぞれ相当自信満々の選手たちばかりで、レベルも相当高い大会となって来ている。
天候が雨模様で選手は相当苦労したようであった。
優勝は男女とも奥州市の選手であった。
これから、仙北道の踏査隊の歓迎会があり、これに出席します。