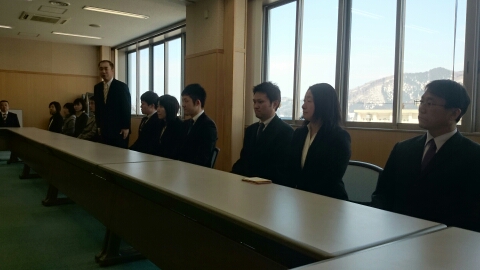(朝焼けが美しい、飛行機雲も見えたが早く消えてしまった。上空はながれが早いんでしょう)

(朝日を背に受けて雪原散歩)
国、県、市町村とも財政状態が厳しくそのための対策として、まずは効率的な運営のために職員数を削減することが最も手っ取り早いとしてその対策に当たってきた。
一方では、高齢化が進み医療、保険などの社会保障対策としての行政対応が、国から地方、特に県を飛び超えて市町村にその対応が回ってきた。
市町村単独ではその運営が無理であることは国民健康保険事業でも明らかになっていることから一部事務組合を作りその運営をするようになってきた。
ところがその組織の職員体制となると、派遣することが原則であるとしているようで、いざ職員派遣となると構成団体の組織規模からいっても簡単に派遣できるような状況ではない、つまり、先に述べたような、職員削減を徹底して進めたことから、余裕のある町村はほとんどないのが現実であり、ほとほと困ってしまっている。
広域市町村圏組合を構成している我々も、何とかそれぞれの構成団体負担金を圧縮すべく消防職員の削減までに取り組むという非常事態的措置までをして取り組んでいる苦しさがある。
一方、国では国民の財産、権利、などの事務事業である業務の人員削減を含め事業所統合にまでも整理の動きが現実としてあり、この後いったいどうなるであろうかと懸念される。
こうした行政課題のつけは、直接的に国民、住民と接する我々に回ってくることは必至であり、覚悟しなければならないことであろうか?
これは、国、県、市町村とも
 (雪割草)
(雪割草)
 (散歩コースの軒下に咲く春の花)
我々自治体職員 の人事管理、労務管理は時代とともに難しさが出て来ている。
我々の職員時代は、一人前にするためには先輩方から徹底して厳しく教えてもらったように感じていた。パワハラなどという言葉さえなかった時代ですし、職場てのイジメなどもあったかどうか?それが今は、常にそうしたことを念頭に置いた対応が迫られているのが現実である。
現実的問題として、関わっている組織でもそうした事例があり、第三者委員会による調査が行われ、その結果が報告された。
結果的には、明確なパワハラスメントとは言いがたいとの報告であった。
但し、職員派遣などに当たっては、派遣する側も受ける側も情報をしっかり共有し確認することや、普段であってもそうした健康管理、労務管理、人事管理をするべきであるとの指摘にはしっかりと心しておかなければならないと、改めて感じたところでした。
次には、2025年を目標にした医療計画の策定に当たっての秋田県医療審議会があり出席。
ぜんかいの計画で大きな話題となり結果として、8二次医療圏に落ち着いたところであったが、今回はこの医療圏構想よりも更に柔軟に考えた構想を策定するための方向で検討することになるように感じた。
何せ、大きな問題であり、総合的に大局的に検討していく問題としてとらえたところでした。
医師サイドからの意見が多く、今後は自治体の取り組みの重要性、この計画は今後の秋田県の医療のあり方の重要なポイントとなるとの意見は理解できた。
これが、総合的なインフラ整備、医師対策、介護問題など地方自治にも大きく関わってくる課題でもあり、ある意味ではチャンスでもあると考えた方がよいとも感じた。
勉強になります。
(散歩コースの軒下に咲く春の花)
我々自治体職員 の人事管理、労務管理は時代とともに難しさが出て来ている。
我々の職員時代は、一人前にするためには先輩方から徹底して厳しく教えてもらったように感じていた。パワハラなどという言葉さえなかった時代ですし、職場てのイジメなどもあったかどうか?それが今は、常にそうしたことを念頭に置いた対応が迫られているのが現実である。
現実的問題として、関わっている組織でもそうした事例があり、第三者委員会による調査が行われ、その結果が報告された。
結果的には、明確なパワハラスメントとは言いがたいとの報告であった。
但し、職員派遣などに当たっては、派遣する側も受ける側も情報をしっかり共有し確認することや、普段であってもそうした健康管理、労務管理、人事管理をするべきであるとの指摘にはしっかりと心しておかなければならないと、改めて感じたところでした。
次には、2025年を目標にした医療計画の策定に当たっての秋田県医療審議会があり出席。
ぜんかいの計画で大きな話題となり結果として、8二次医療圏に落ち着いたところであったが、今回はこの医療圏構想よりも更に柔軟に考えた構想を策定するための方向で検討することになるように感じた。
何せ、大きな問題であり、総合的に大局的に検討していく問題としてとらえたところでした。
医師サイドからの意見が多く、今後は自治体の取り組みの重要性、この計画は今後の秋田県の医療のあり方の重要なポイントとなるとの意見は理解できた。
これが、総合的なインフラ整備、医師対策、介護問題など地方自治にも大きく関わってくる課題でもあり、ある意味ではチャンスでもあると考えた方がよいとも感じた。
勉強になります。