 村の新たな発展計画を策定したことを含めて、全村4地域で、住民の方々にその発展計画をお示すするほか、それぞれの地域の抱える課題についての意見交換をし今後の村政運営の大いなる参考にさせていただくために今年も開催することにした。
今年は、農作業の進み具合と合わせて計画したところでしたが、農家の方々の都合がどうであったか多少心配していた。
一日目は、一番人口の多い田子内地区での座談会で14名の方々が集まってくれた。
これまで、この地域では他の地域よりは比較的集まってくれる方が少なっかったが、今回はこれまでよりは多く集まってくれたような気がした。
今後重点的に進めていく事業や、総合発展計画の概要などを説明し、さらに村として取り組んでいる事業について、それぞれの所管から説明と協力依頼をしたところでした。
その後、参加者から、地域での課題やら、説明についての質問が活発に行われ、しっかりとお答えしたところでした。
やはりこうした形で、住民の方々と直接村政課題について話し合うことは、理解をいただくことにもつながるし、村民の意見を聞いて村政運営をしていくための重要な対応策であると考えているし、議会での議論とともに、住民がどう考えているかを少なくとも参加された方々のご意見はうかがうことができることになると思う。
今後も、こうした企画は継続して続けていきたいと考えているところである。
質問事項も、10数項目に上った。
ありがとうございました。
村の新たな発展計画を策定したことを含めて、全村4地域で、住民の方々にその発展計画をお示すするほか、それぞれの地域の抱える課題についての意見交換をし今後の村政運営の大いなる参考にさせていただくために今年も開催することにした。
今年は、農作業の進み具合と合わせて計画したところでしたが、農家の方々の都合がどうであったか多少心配していた。
一日目は、一番人口の多い田子内地区での座談会で14名の方々が集まってくれた。
これまで、この地域では他の地域よりは比較的集まってくれる方が少なっかったが、今回はこれまでよりは多く集まってくれたような気がした。
今後重点的に進めていく事業や、総合発展計画の概要などを説明し、さらに村として取り組んでいる事業について、それぞれの所管から説明と協力依頼をしたところでした。
その後、参加者から、地域での課題やら、説明についての質問が活発に行われ、しっかりとお答えしたところでした。
やはりこうした形で、住民の方々と直接村政課題について話し合うことは、理解をいただくことにもつながるし、村民の意見を聞いて村政運営をしていくための重要な対応策であると考えているし、議会での議論とともに、住民がどう考えているかを少なくとも参加された方々のご意見はうかがうことができることになると思う。
今後も、こうした企画は継続して続けていきたいと考えているところである。
質問事項も、10数項目に上った。
ありがとうございました。 座談会を始める
 村の新たな発展計画を策定したことを含めて、全村4地域で、住民の方々にその発展計画をお示すするほか、それぞれの地域の抱える課題についての意見交換をし今後の村政運営の大いなる参考にさせていただくために今年も開催することにした。
今年は、農作業の進み具合と合わせて計画したところでしたが、農家の方々の都合がどうであったか多少心配していた。
一日目は、一番人口の多い田子内地区での座談会で14名の方々が集まってくれた。
これまで、この地域では他の地域よりは比較的集まってくれる方が少なっかったが、今回はこれまでよりは多く集まってくれたような気がした。
今後重点的に進めていく事業や、総合発展計画の概要などを説明し、さらに村として取り組んでいる事業について、それぞれの所管から説明と協力依頼をしたところでした。
その後、参加者から、地域での課題やら、説明についての質問が活発に行われ、しっかりとお答えしたところでした。
やはりこうした形で、住民の方々と直接村政課題について話し合うことは、理解をいただくことにもつながるし、村民の意見を聞いて村政運営をしていくための重要な対応策であると考えているし、議会での議論とともに、住民がどう考えているかを少なくとも参加された方々のご意見はうかがうことができることになると思う。
今後も、こうした企画は継続して続けていきたいと考えているところである。
質問事項も、10数項目に上った。
ありがとうございました。
村の新たな発展計画を策定したことを含めて、全村4地域で、住民の方々にその発展計画をお示すするほか、それぞれの地域の抱える課題についての意見交換をし今後の村政運営の大いなる参考にさせていただくために今年も開催することにした。
今年は、農作業の進み具合と合わせて計画したところでしたが、農家の方々の都合がどうであったか多少心配していた。
一日目は、一番人口の多い田子内地区での座談会で14名の方々が集まってくれた。
これまで、この地域では他の地域よりは比較的集まってくれる方が少なっかったが、今回はこれまでよりは多く集まってくれたような気がした。
今後重点的に進めていく事業や、総合発展計画の概要などを説明し、さらに村として取り組んでいる事業について、それぞれの所管から説明と協力依頼をしたところでした。
その後、参加者から、地域での課題やら、説明についての質問が活発に行われ、しっかりとお答えしたところでした。
やはりこうした形で、住民の方々と直接村政課題について話し合うことは、理解をいただくことにもつながるし、村民の意見を聞いて村政運営をしていくための重要な対応策であると考えているし、議会での議論とともに、住民がどう考えているかを少なくとも参加された方々のご意見はうかがうことができることになると思う。
今後も、こうした企画は継続して続けていきたいと考えているところである。
質問事項も、10数項目に上った。
ありがとうございました。 



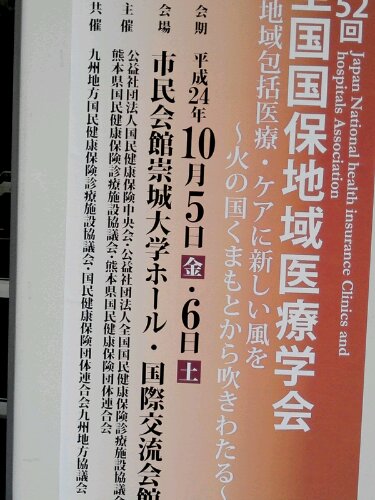

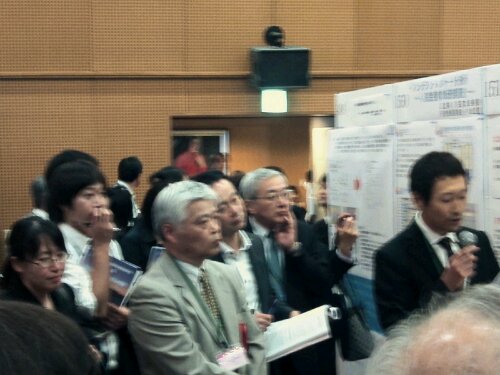 第52回全国国保地域医療学会に出席した。
今年の開催地が熊本市で、村からは3名が出席した。
この学会は「地域包括医療・ケアに新しい風を~火の国くまもとから吹きわたる~」をテーマにしている。
このテーマは、地域医療を医療と福祉を包括的に考え、より良い住民の健康、福祉のあり方を追求しつつ実現していこうとするものと考えている。
この学会には、国保関係の医師、保健師、看護士、検査技師、療法士、技師、事務職など幅広い分野の職種が研究した成果をポスターに
第52回全国国保地域医療学会に出席した。
今年の開催地が熊本市で、村からは3名が出席した。
この学会は「地域包括医療・ケアに新しい風を~火の国くまもとから吹きわたる~」をテーマにしている。
このテーマは、地域医療を医療と福祉を包括的に考え、より良い住民の健康、福祉のあり方を追求しつつ実現していこうとするものと考えている。
この学会には、国保関係の医師、保健師、看護士、検査技師、療法士、技師、事務職など幅広い分野の職種が研究した成果をポスターに
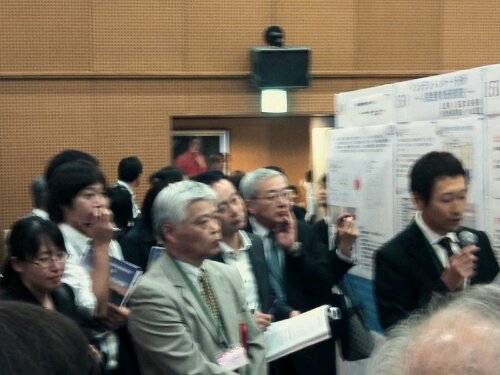 して掲示し意見発表をし、会場との意見交換をして以後の活動に役立てている。
普段そうした活動がなく、ただ忙しく毎日を過ごすのではなく、目的を持って、診療所などの医療活動、保健活動、指導などを福祉を含めて包括的に活動していく必要を私は強く感じている。
これを、これからはさらに福祉施設、ケアネを含めた関係者が一体となった活動にも連携がとれるようにしていけらより一層効果が出てくるものと考えている。
こうした方向にいくように、少しずつ近づけたらと願っているし、期待したい。
この学会では、診療所などの施設開設者としての、首長も出席している。
これには、在宅医療、診療報酬改定、施設整備、医師確保、在宅介護、など幅広い分野からの地域包括医療の連携などを議論、研究しあう学会で、ここから全国的な地域医療の方向性を確認しつつ、そのありかたをしっかりととらえたいと感じている。
単に同じ悩みがあることを知るばかりではなく、今後の有り様を考える大事な学会ととらえている。
この地域包括医療の考え方は、山口昇広島県みつぎ総合病院の名誉院長が提唱した制度であり、既に38年を経過しているとのこと。
我々首長は住民の船頭役として頑張るべきとの山形県小国町立病院の阿部院長さんの提唱に、心してがんばらなければならないと強く感じた
して掲示し意見発表をし、会場との意見交換をして以後の活動に役立てている。
普段そうした活動がなく、ただ忙しく毎日を過ごすのではなく、目的を持って、診療所などの医療活動、保健活動、指導などを福祉を含めて包括的に活動していく必要を私は強く感じている。
これを、これからはさらに福祉施設、ケアネを含めた関係者が一体となった活動にも連携がとれるようにしていけらより一層効果が出てくるものと考えている。
こうした方向にいくように、少しずつ近づけたらと願っているし、期待したい。
この学会では、診療所などの施設開設者としての、首長も出席している。
これには、在宅医療、診療報酬改定、施設整備、医師確保、在宅介護、など幅広い分野からの地域包括医療の連携などを議論、研究しあう学会で、ここから全国的な地域医療の方向性を確認しつつ、そのありかたをしっかりととらえたいと感じている。
単に同じ悩みがあることを知るばかりではなく、今後の有り様を考える大事な学会ととらえている。
この地域包括医療の考え方は、山口昇広島県みつぎ総合病院の名誉院長が提唱した制度であり、既に38年を経過しているとのこと。
我々首長は住民の船頭役として頑張るべきとの山形県小国町立病院の阿部院長さんの提唱に、心してがんばらなければならないと強く感じた
 。
。