
(選定の背景について、ご本人がさらっと説明するとしてシンポジュームの初めに講演してくれた、文化庁の伝統的建造物担当主任文化財調査官の挨拶)

(昨年選定されての公開記念イベントでも紹介された、民俗芸能の福島サイサイ囃子も賑やかに紹介された)
我が村のとなり町、横手市増田町の昔ながらの建物、特に内蔵を備えた母屋の建物が国の「重要伝統的建造物群保存地区」として選定されたことを記念してのシンポジュームが開かれた。
私たちは、普段見慣れた建物ぐらいに感じており、特にそんなに関心があったわけでは無かったのですが、こうした形で昔の街道、つまり道路に面してこんなに多くの木造建築物としかも内蔵を有した建造物群は日本でも希有の存在であるとの文化庁の主任調査官から選定の背景などの説明を受けて改めてその意義を感じた次第でした。
特に、その母屋部分だけでも大きな価値があり、更には内蔵までも含めると、それはそれは大変に重要な建造物群であるとのことに、認識を新たにしたところでした。
その蔵の建設に至るいきさつについては、我が村の古老の方々からお聞きしたことを含め、増田の郷土史などを研究されておられる方々のご意見をお聞きすると、結構複雑な想いがしないわけでもありませんし、私どもが主催して開いた「仙北道を考える」ブナ林の古道のシンポジュームでも、その歴史的背景については、郷土史を研究されておられる方の意見発表でもそのことについてはふれられておったことを思い出しました。
それはそれとして、今日このように意義ある選定のために、もう10年近くも前からこうした運動を展開されておった旧増田町の役場関係者、そうした重要な建物を保有されておられた旧地主さんたちや商家の方々の並々ならぬご努力と理解に敬意を改めて表したいと思うところです。
近場にこうした建造物群があることは今後も大きな誇りであり、大いに全国に発信してほしいと考えるし、我々の村を訪れた方々に対しても理解を深めていただき視察研修、交流を深めあうようにご協力をしたいものですし、交流しあいたいものです。
既に、わが村を訪れておられる方々には、コースとして「まんが美術館」と、それこそ伝統的保存建造物群の蔵を修復し、今後500年は持つとまで言われている稲庭うどんのレストランに改造している施設をコースに入れて紹介をさせていただいている。
これらに加えてのコースにすることはおおきなインパクトを与えることになろうかと思われる。
懇親会では、この指定は「市町村合併の効果である」と有力な市会議員の方が私にお話をかけてこられたが、どんな意味だったんだろうと今も不思議でならない。
それがなければ、地元の有力者からはとてもとても理解が得られなかったとのことでした。
そうだったんだろうか?市町村合併前からこの選定に向けての運動は静かに深く潜行して進められていたとのことでしたが・・・・・・・。
更に、東成瀬には「山菜をどんどんとって売ってもらいたい」とかといった昔ながらの増田と東成瀬の関係から一歩も踏み出さない、そんな役割としかないような感覚には少し残念であったのは、私のひがんだ感覚なのかなーと思ってしまった。




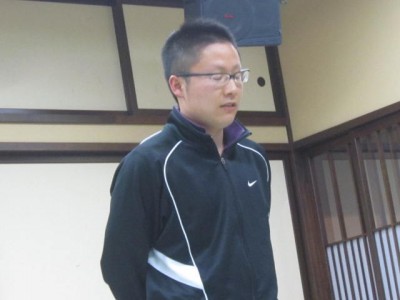


 昨日の夕方、村のジュニアアルペンスキークラブ(JJR・ジュネス・ジュニアレーシングクラブ)の今シーズンの中間報告会が開かれ子供たちと親が一緒になり、このクラブの指導を行っているコーチたちとの中間報告会があり、呼んでくれたので出かけた。
最初はいつも通りの進行であったが、1時間ほどしてからの報告会が俄然と熱を帯びてきた。
始めに、中学生に対して今シーズンのこれまでの競技会での、自分で足りなかった点を一つ、練習での反省点、さらに今後の目標を述べなさいと、コーチから求められ、それに対して中学生はしっかりと自分の考えを述べていたことには驚かされた。
技術的な面はもとより、指摘されていたことをしっかりとおぼえており、それに対する今後の自分の努力目標をしっかりと持っていることに感心させられた。
また、小学生に対しても、これまでの大会での反省点、これからどんな人の滑りを目標にしたいかなどと極めて具体的にそれぞれの考えを話すように求められているのに対し、小学校3年生からの子供たちがこれまたしっかりと話していた。
久しぶりにこの会に出席したが、すっかり様変わりしていたし、何よりも親がおる前で、コーチの面々が鋭く指摘し、親子ともどもに考えさせらるように指導していたことに驚きを感じた。
しかも、親たちの中には先輩コーチがおり、そのコーチから指導してもらったコーチたちである中で、堂々と指導方針、子供たちに欠けていることを、鋭く指摘していた。
確かな後継者がしっかりと育っていることをこの目で確認し、その雰囲気をしっかりと感じることができ、とてもうれしかったし、頼もしくも感じたところでした。
確実にこうした指導者が育ち、スキーの普及のために、お互いが連携し合えるような体制になっていることにものすごい充実感を感じてうれしかった。
中間報告会は子供たちと一緒の食事会でもあるし、親たちとコーチの懇親会でもある。
そんな中でも、食事は食事、飲み会は飲み会、話は聞くときは聞く、しっかりとしたけじめをつけたこうした報告会は素晴らしいと思った。
こうした中から、全国スキー大会にも出場するといった成績をしっかりと残していることは素晴らしいことであり、これからもしっかりと応援をしていきたいと思っている。
いやー、本当に頼もしく感じられた報告会でした。
昨日の夕方、村のジュニアアルペンスキークラブ(JJR・ジュネス・ジュニアレーシングクラブ)の今シーズンの中間報告会が開かれ子供たちと親が一緒になり、このクラブの指導を行っているコーチたちとの中間報告会があり、呼んでくれたので出かけた。
最初はいつも通りの進行であったが、1時間ほどしてからの報告会が俄然と熱を帯びてきた。
始めに、中学生に対して今シーズンのこれまでの競技会での、自分で足りなかった点を一つ、練習での反省点、さらに今後の目標を述べなさいと、コーチから求められ、それに対して中学生はしっかりと自分の考えを述べていたことには驚かされた。
技術的な面はもとより、指摘されていたことをしっかりとおぼえており、それに対する今後の自分の努力目標をしっかりと持っていることに感心させられた。
また、小学生に対しても、これまでの大会での反省点、これからどんな人の滑りを目標にしたいかなどと極めて具体的にそれぞれの考えを話すように求められているのに対し、小学校3年生からの子供たちがこれまたしっかりと話していた。
久しぶりにこの会に出席したが、すっかり様変わりしていたし、何よりも親がおる前で、コーチの面々が鋭く指摘し、親子ともどもに考えさせらるように指導していたことに驚きを感じた。
しかも、親たちの中には先輩コーチがおり、そのコーチから指導してもらったコーチたちである中で、堂々と指導方針、子供たちに欠けていることを、鋭く指摘していた。
確かな後継者がしっかりと育っていることをこの目で確認し、その雰囲気をしっかりと感じることができ、とてもうれしかったし、頼もしくも感じたところでした。
確実にこうした指導者が育ち、スキーの普及のために、お互いが連携し合えるような体制になっていることにものすごい充実感を感じてうれしかった。
中間報告会は子供たちと一緒の食事会でもあるし、親たちとコーチの懇親会でもある。
そんな中でも、食事は食事、飲み会は飲み会、話は聞くときは聞く、しっかりとしたけじめをつけたこうした報告会は素晴らしいと思った。
こうした中から、全国スキー大会にも出場するといった成績をしっかりと残していることは素晴らしいことであり、これからもしっかりと応援をしていきたいと思っている。
いやー、本当に頼もしく感じられた報告会でした。 











