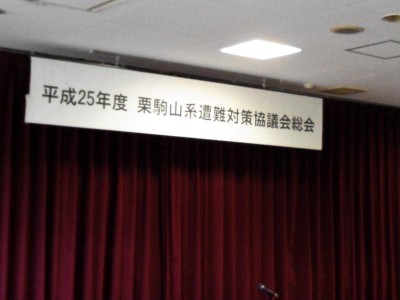いよいよいろんな団体の予算要望の為の理事会、総会、要望会が全国レベルでの開催が始まった。
多くの要望が出されるが、今回の
理事会では、過疎地でのラジオ放送の難視聴、特に、NHKの受信が出来ない地域対策について、発言させてもらった。
なかなか、中央では理解をいただけないかも知れませんが、発言しないことには、埒があきませんので、これまでも、機会あるごとに発言してきたし、要望もしたのでるが、さっぱり動きがなく、今回は、過疎連盟の理事会の場で発言した。お
過疎対策室長もお見えでしたので、名刺交換を兼ねて、実情を話したところ、九州の理事さんも
聞こえないんだよなーとはなしておられた。
関係者と話してみるとのことで、後で回答か対応策が連絡いただけるものと思った。
会長さんも事務局に指示してくれたようです。
ところで、上京に利用した飛行機が、問題のB787で、先日もバッテリーに不具合があったとかで、運航が中止されたようだが、今回は全く問題なく飛びました。
客席は広い感じで、8列もありいい感じでしたし、何より新しいので感じがよかった!
いよいよいろんな団体の予算要望の為の理事会、総会、要望会が全国レベルでの開催が始まった。
多くの要望が出されるが、今回の
理事会では、過疎地でのラジオ放送の難視聴、特に、NHKの受信が出来ない地域対策について、発言させてもらった。
なかなか、中央では理解をいただけないかも知れませんが、発言しないことには、埒があきませんので、これまでも、機会あるごとに発言してきたし、要望もしたのでるが、さっぱり動きがなく、今回は、過疎連盟の理事会の場で発言した。お
過疎対策室長もお見えでしたので、名刺交換を兼ねて、実情を話したところ、九州の理事さんも
聞こえないんだよなーとはなしておられた。
関係者と話してみるとのことで、後で回答か対応策が連絡いただけるものと思った。
会長さんも事務局に指示してくれたようです。
ところで、上京に利用した飛行機が、問題のB787で、先日もバッテリーに不具合があったとかで、運航が中止されたようだが、今回は全く問題なく飛びました。
客席は広い感じで、8列もありいい感じでしたし、何より新しいので感じがよかった!