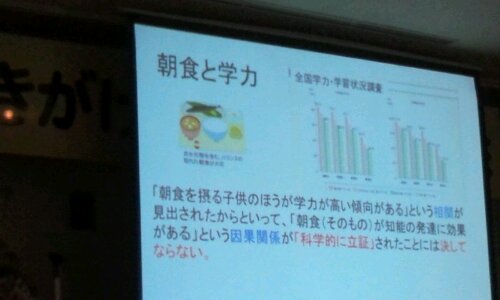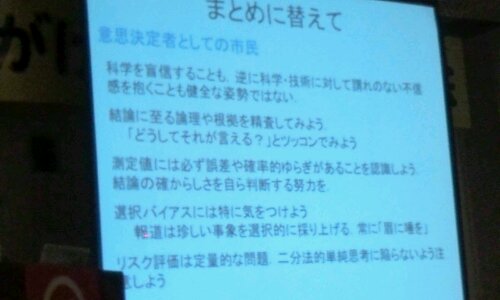いろいろと心配された第29回国民文化祭が皇太子殿下をお迎えして、賑やかにしかも盛大にオープニングセレモニーが県立武道館で行われた。
武道館でのこうした、セレモニーは私は初めてであるが、音響効果も良く会場設定はよかった。全体的に凄く洗練された演出で、随所に秋田の特色をちりばめつつ、若い世代をふんだんに登場させ、バレーやダンス、一輪車による素晴らしい演技と踊りまでも登場し観客を驚かせていた。その演技に技術は高いものであったと感じた。
秋田の伝統芸能はほとんど網羅していましたし、新しい音楽、バレーが融和し、しかも嫌みもなくテンポよく、スピーディーな演出はあっという間の2時間30分でした。
大いなる秋田の吹奏楽と管弦楽に合唱は見事にコラボレーションし感動的でした。
総勢800名からなる大合唱たと演奏は圧巻であり、感動で思わず涙がにじむようでさえあった。
「発見・創造 ・もうひとつの秋田」のテーマにばっちりであったし、「新しい発見を求め文化を巡る旅にでかけよう」と本当にそんな気にさせるオープニングであった。
当然のことながら、写真撮影禁止で載せられないのが残念!
テレビで放映されましょうし、DVDも出されると思うので是非ご覧になってください。
わが村の「昔しっこの祭典」は、県内110の企画では唯一であり、キラリと光るような気がするなー!
昨年のプレイベントの参加からしてもそんな感じがする。
我が村は、そうした文化面、教育面などでじわりじわりと小さいながらも着実に特徴付けれるような取り組みを基本にしていきたいものであるし、それが海外とも連携出来るように出来たら最高だなー!
近くデンバーからお客さんも来るし、交流再開を打診したらどうだろうか?
そんなことを考え帰路についたところでした。
いろいろと心配された第29回国民文化祭が皇太子殿下をお迎えして、賑やかにしかも盛大にオープニングセレモニーが県立武道館で行われた。
武道館でのこうした、セレモニーは私は初めてであるが、音響効果も良く会場設定はよかった。全体的に凄く洗練された演出で、随所に秋田の特色をちりばめつつ、若い世代をふんだんに登場させ、バレーやダンス、一輪車による素晴らしい演技と踊りまでも登場し観客を驚かせていた。その演技に技術は高いものであったと感じた。
秋田の伝統芸能はほとんど網羅していましたし、新しい音楽、バレーが融和し、しかも嫌みもなくテンポよく、スピーディーな演出はあっという間の2時間30分でした。
大いなる秋田の吹奏楽と管弦楽に合唱は見事にコラボレーションし感動的でした。
総勢800名からなる大合唱たと演奏は圧巻であり、感動で思わず涙がにじむようでさえあった。
「発見・創造 ・もうひとつの秋田」のテーマにばっちりであったし、「新しい発見を求め文化を巡る旅にでかけよう」と本当にそんな気にさせるオープニングであった。
当然のことながら、写真撮影禁止で載せられないのが残念!
テレビで放映されましょうし、DVDも出されると思うので是非ご覧になってください。
わが村の「昔しっこの祭典」は、県内110の企画では唯一であり、キラリと光るような気がするなー!
昨年のプレイベントの参加からしてもそんな感じがする。
我が村は、そうした文化面、教育面などでじわりじわりと小さいながらも着実に特徴付けれるような取り組みを基本にしていきたいものであるし、それが海外とも連携出来るように出来たら最高だなー!
近くデンバーからお客さんも来るし、交流再開を打診したらどうだろうか?
そんなことを考え帰路についたところでした。 










![DSC_0004[2]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/07/DSC_00042-500x280.jpg)
![DSC_0022[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/07/DSC_00221-500x280.jpg)
![DSC_0006[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/07/DSC_00061-500x280.jpg)
![DSC_0018[1]](http://blog.higashinaruse.com/sennin_blog_01/wp-content/uploads/2014/07/DSC_00181-500x280.jpg)