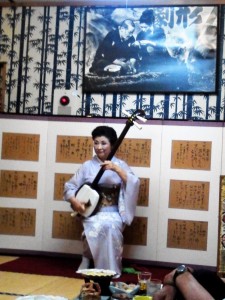お盆が過ぎると、私たちの周囲にもかすかな変化が日に日に感じられてくる。
暦でもそうですが、今日は「処暑」、夏の暑さが和らぎ、暑さの峠を越える頃で、萩の花も咲きだす頃、そう言えば、先日の朝の散歩でその花を見かけた、そんな24節気での一つであるそうですが、まさしく暦通りの天候になりつつある。
一方で、東日本、西日本では暑さが続き、雨のほしい地域や、ダムの水も干上がり、取水制限など厳しい状況であるようです。
先日帰省した息子の住む、沖縄那覇も連日30度を越しておるばかりか、もう台風12号が発生近づいているとの情報に気を病んでもいる。孫たちも暑いだろうなどと。
こちらの孫も夏休みも終わりに近づき、宿題の仕上げが大忙し。
そんな朝、空にも微妙な変化があり、雲の変化を見るのもまた楽しいひと時である。
お盆が過ぎると、私たちの周囲にもかすかな変化が日に日に感じられてくる。
暦でもそうですが、今日は「処暑」、夏の暑さが和らぎ、暑さの峠を越える頃で、萩の花も咲きだす頃、そう言えば、先日の朝の散歩でその花を見かけた、そんな24節気での一つであるそうですが、まさしく暦通りの天候になりつつある。
一方で、東日本、西日本では暑さが続き、雨のほしい地域や、ダムの水も干上がり、取水制限など厳しい状況であるようです。
先日帰省した息子の住む、沖縄那覇も連日30度を越しておるばかりか、もう台風12号が発生近づいているとの情報に気を病んでもいる。孫たちも暑いだろうなどと。
こちらの孫も夏休みも終わりに近づき、宿題の仕上げが大忙し。
そんな朝、空にも微妙な変化があり、雲の変化を見るのもまた楽しいひと時である。