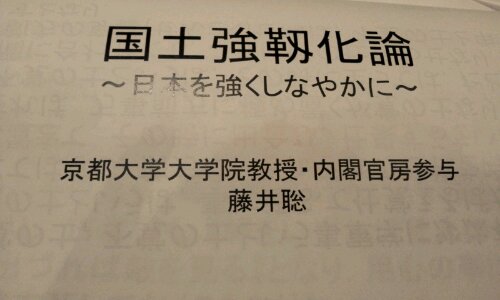(来賓挨拶をされる総務省の関・地域力創造審議官)
全国過疎地域自立促進連盟(会長・島根県知事)の理事会が開かれ出席した。
秋田からは県議会からも出席されておった。
理事会議案は新年度の予算、事業などについて審議し原案通り承認されたが、この関係法案は議員立法であることから、政府与党の特別委員会で一昨日議決決定され、今国会に提案されることになっていることから、その成立について理事各位の国会議員に対する要請活動を徹底するよう要請された。
また、次期対策についても、与党においては、期限切れとなる3年後の改訂に向けて既にその法案の概要が審議されており、安倍内閣の日本の隅々まで政府の政策が行き渡るような体制下にあるように感じられた。
来賓として出席された関・総務相地域力創造審議官からは、過疎法の見直しが与党内手続きが終了し決定した、ソフト事業も活用が増えたこと、アベノミクスが徹底される重要な一年になること、交付金の増額、集落機能の活性化対策の重要性と過疎債の活用、地域活力イノベーション対策の充実、定住自立圏、地域興し協力隊の増加と活用などについての支援強化活用が求められたところでした。
法案の一部改正については、過疎団体の追加があるようで、秋田県では八郎潟町が新たに過疎指定されるようでした。
また、過疎対策事業債の対象拡充、指定団体の基準拡大など過疎自治体にとっては一定の進展が図られたようである。
この会議の後に、もと厚生労働省事務次官であった方の講演があった。
演題は「超高齢化社会における医療介護政策の展望」と題するもので、大都市圏において、超高齢化社会、つまり2025年度問題が到来するという極めて現実的な問題に対する対応策についての提言であった。
大都市問題なのになぜ、過疎団体の集まりでの講演なのかいささか腑に落ちない面もあったが、これは、大都市だけの問題ではなく、日本全体にも係わる重要な問題であるとも感じた。
講師も、そこいらへんについては多少気になさっておられたようで、何回も都市問題として研究しておられることを強調されていた。
しかし、高齢化と医療介護、少子化と子育て、労働人口対策などは一体で考えなければならない課題であり、同時に解決しなければならないきわめて難しいが、日本全体の問題ととらえる必要があることには間違いない問題であろうと感じたし、講師もそこを強調しておられた。
具体的には、団塊の世代が2025年には高齢化社会の中心になり、ここの世代をどう活用するか、同時に介護の問題もこの世代を中心にして急速にふくらんでくる。
そのための対策、介護問題に関わる医療と福祉の問題、特に最近特に強調されている「地域包括ケア」を実現するための施策(医療との連携強化、介護サービスの充実強化、予防の推進、見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービス、高齢者住宅対策)の重要性が述べられていた。
地域医療についても、開業医と病院の役割分担の関係の重要性、医師会と市町村との連携、支える医療の方向性は揺るがないであろうし、これからの医療のあり方も、今回の診療報酬改定もその方向に動き出しておるとの見解でした。
これまでの経験、研究などを元にした提言であり、確かな情報での講演であると思った。
(来賓挨拶をされる総務省の関・地域力創造審議官)
全国過疎地域自立促進連盟(会長・島根県知事)の理事会が開かれ出席した。
秋田からは県議会からも出席されておった。
理事会議案は新年度の予算、事業などについて審議し原案通り承認されたが、この関係法案は議員立法であることから、政府与党の特別委員会で一昨日議決決定され、今国会に提案されることになっていることから、その成立について理事各位の国会議員に対する要請活動を徹底するよう要請された。
また、次期対策についても、与党においては、期限切れとなる3年後の改訂に向けて既にその法案の概要が審議されており、安倍内閣の日本の隅々まで政府の政策が行き渡るような体制下にあるように感じられた。
来賓として出席された関・総務相地域力創造審議官からは、過疎法の見直しが与党内手続きが終了し決定した、ソフト事業も活用が増えたこと、アベノミクスが徹底される重要な一年になること、交付金の増額、集落機能の活性化対策の重要性と過疎債の活用、地域活力イノベーション対策の充実、定住自立圏、地域興し協力隊の増加と活用などについての支援強化活用が求められたところでした。
法案の一部改正については、過疎団体の追加があるようで、秋田県では八郎潟町が新たに過疎指定されるようでした。
また、過疎対策事業債の対象拡充、指定団体の基準拡大など過疎自治体にとっては一定の進展が図られたようである。
この会議の後に、もと厚生労働省事務次官であった方の講演があった。
演題は「超高齢化社会における医療介護政策の展望」と題するもので、大都市圏において、超高齢化社会、つまり2025年度問題が到来するという極めて現実的な問題に対する対応策についての提言であった。
大都市問題なのになぜ、過疎団体の集まりでの講演なのかいささか腑に落ちない面もあったが、これは、大都市だけの問題ではなく、日本全体にも係わる重要な問題であるとも感じた。
講師も、そこいらへんについては多少気になさっておられたようで、何回も都市問題として研究しておられることを強調されていた。
しかし、高齢化と医療介護、少子化と子育て、労働人口対策などは一体で考えなければならない課題であり、同時に解決しなければならないきわめて難しいが、日本全体の問題ととらえる必要があることには間違いない問題であろうと感じたし、講師もそこを強調しておられた。
具体的には、団塊の世代が2025年には高齢化社会の中心になり、ここの世代をどう活用するか、同時に介護の問題もこの世代を中心にして急速にふくらんでくる。
そのための対策、介護問題に関わる医療と福祉の問題、特に最近特に強調されている「地域包括ケア」を実現するための施策(医療との連携強化、介護サービスの充実強化、予防の推進、見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービス、高齢者住宅対策)の重要性が述べられていた。
地域医療についても、開業医と病院の役割分担の関係の重要性、医師会と市町村との連携、支える医療の方向性は揺るがないであろうし、これからの医療のあり方も、今回の診療報酬改定もその方向に動き出しておるとの見解でした。
これまでの経験、研究などを元にした提言であり、確かな情報での講演であると思った。
過疎連盟理事会
 (来賓挨拶をされる総務省の関・地域力創造審議官)
全国過疎地域自立促進連盟(会長・島根県知事)の理事会が開かれ出席した。
秋田からは県議会からも出席されておった。
理事会議案は新年度の予算、事業などについて審議し原案通り承認されたが、この関係法案は議員立法であることから、政府与党の特別委員会で一昨日議決決定され、今国会に提案されることになっていることから、その成立について理事各位の国会議員に対する要請活動を徹底するよう要請された。
また、次期対策についても、与党においては、期限切れとなる3年後の改訂に向けて既にその法案の概要が審議されており、安倍内閣の日本の隅々まで政府の政策が行き渡るような体制下にあるように感じられた。
来賓として出席された関・総務相地域力創造審議官からは、過疎法の見直しが与党内手続きが終了し決定した、ソフト事業も活用が増えたこと、アベノミクスが徹底される重要な一年になること、交付金の増額、集落機能の活性化対策の重要性と過疎債の活用、地域活力イノベーション対策の充実、定住自立圏、地域興し協力隊の増加と活用などについての支援強化活用が求められたところでした。
法案の一部改正については、過疎団体の追加があるようで、秋田県では八郎潟町が新たに過疎指定されるようでした。
また、過疎対策事業債の対象拡充、指定団体の基準拡大など過疎自治体にとっては一定の進展が図られたようである。
この会議の後に、もと厚生労働省事務次官であった方の講演があった。
演題は「超高齢化社会における医療介護政策の展望」と題するもので、大都市圏において、超高齢化社会、つまり2025年度問題が到来するという極めて現実的な問題に対する対応策についての提言であった。
大都市問題なのになぜ、過疎団体の集まりでの講演なのかいささか腑に落ちない面もあったが、これは、大都市だけの問題ではなく、日本全体にも係わる重要な問題であるとも感じた。
講師も、そこいらへんについては多少気になさっておられたようで、何回も都市問題として研究しておられることを強調されていた。
しかし、高齢化と医療介護、少子化と子育て、労働人口対策などは一体で考えなければならない課題であり、同時に解決しなければならないきわめて難しいが、日本全体の問題ととらえる必要があることには間違いない問題であろうと感じたし、講師もそこを強調しておられた。
具体的には、団塊の世代が2025年には高齢化社会の中心になり、ここの世代をどう活用するか、同時に介護の問題もこの世代を中心にして急速にふくらんでくる。
そのための対策、介護問題に関わる医療と福祉の問題、特に最近特に強調されている「地域包括ケア」を実現するための施策(医療との連携強化、介護サービスの充実強化、予防の推進、見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービス、高齢者住宅対策)の重要性が述べられていた。
地域医療についても、開業医と病院の役割分担の関係の重要性、医師会と市町村との連携、支える医療の方向性は揺るがないであろうし、これからの医療のあり方も、今回の診療報酬改定もその方向に動き出しておるとの見解でした。
これまでの経験、研究などを元にした提言であり、確かな情報での講演であると思った。
(来賓挨拶をされる総務省の関・地域力創造審議官)
全国過疎地域自立促進連盟(会長・島根県知事)の理事会が開かれ出席した。
秋田からは県議会からも出席されておった。
理事会議案は新年度の予算、事業などについて審議し原案通り承認されたが、この関係法案は議員立法であることから、政府与党の特別委員会で一昨日議決決定され、今国会に提案されることになっていることから、その成立について理事各位の国会議員に対する要請活動を徹底するよう要請された。
また、次期対策についても、与党においては、期限切れとなる3年後の改訂に向けて既にその法案の概要が審議されており、安倍内閣の日本の隅々まで政府の政策が行き渡るような体制下にあるように感じられた。
来賓として出席された関・総務相地域力創造審議官からは、過疎法の見直しが与党内手続きが終了し決定した、ソフト事業も活用が増えたこと、アベノミクスが徹底される重要な一年になること、交付金の増額、集落機能の活性化対策の重要性と過疎債の活用、地域活力イノベーション対策の充実、定住自立圏、地域興し協力隊の増加と活用などについての支援強化活用が求められたところでした。
法案の一部改正については、過疎団体の追加があるようで、秋田県では八郎潟町が新たに過疎指定されるようでした。
また、過疎対策事業債の対象拡充、指定団体の基準拡大など過疎自治体にとっては一定の進展が図られたようである。
この会議の後に、もと厚生労働省事務次官であった方の講演があった。
演題は「超高齢化社会における医療介護政策の展望」と題するもので、大都市圏において、超高齢化社会、つまり2025年度問題が到来するという極めて現実的な問題に対する対応策についての提言であった。
大都市問題なのになぜ、過疎団体の集まりでの講演なのかいささか腑に落ちない面もあったが、これは、大都市だけの問題ではなく、日本全体にも係わる重要な問題であるとも感じた。
講師も、そこいらへんについては多少気になさっておられたようで、何回も都市問題として研究しておられることを強調されていた。
しかし、高齢化と医療介護、少子化と子育て、労働人口対策などは一体で考えなければならない課題であり、同時に解決しなければならないきわめて難しいが、日本全体の問題ととらえる必要があることには間違いない問題であろうと感じたし、講師もそこを強調しておられた。
具体的には、団塊の世代が2025年には高齢化社会の中心になり、ここの世代をどう活用するか、同時に介護の問題もこの世代を中心にして急速にふくらんでくる。
そのための対策、介護問題に関わる医療と福祉の問題、特に最近特に強調されている「地域包括ケア」を実現するための施策(医療との連携強化、介護サービスの充実強化、予防の推進、見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービス、高齢者住宅対策)の重要性が述べられていた。
地域医療についても、開業医と病院の役割分担の関係の重要性、医師会と市町村との連携、支える医療の方向性は揺るがないであろうし、これからの医療のあり方も、今回の診療報酬改定もその方向に動き出しておるとの見解でした。
これまでの経験、研究などを元にした提言であり、確かな情報での講演であると思った。