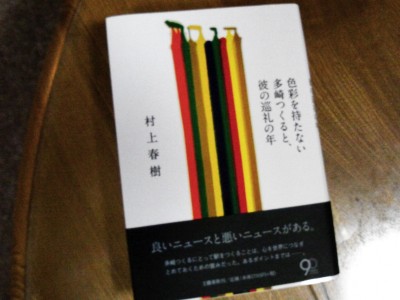いよいよ春本番となる。
野山の花も咲きだし桜の芽も膨らも出してきているようだ。
私の家の周辺でも花が咲きだして、これからが楽しみです。
フクジュソウは今が真っ盛り、スイセンも咲きだした。レンギョウもかすかに膨らみだしたし、我が家の庭の山野草もいよいよ芽を出してくる頃である。
これには決して手を出されない。
なぜかというと、草取りと称して草むしりをすると、それがかみさんが大事にしていた山野草であることがこれまで何度あったことか。
その都度きついおしかりを受けており、今度こそは絶対そうしたものには手を出さないようにしようと思うのだが、ついつい手を出してしまう。
山野草は一見して雑草と変わらないように見えるが、一旦咲くとそれはそれはとても可憐な花をつける。
ごく一般的な花であっても、その花の名もよく知らない私にとっては、本当に見分けが付けにくいのである。
ましてや山野草となるとますますわからない、毎年河北新報の金曜日夕刊では「栗駒便り」で栗駒山の山野草を村のH氏が紹介しているし、毎日新聞では湯沢の方が草花を紹介している、フエースブックでは、湯沢市役所OBのS氏が丁寧に折々の草花を紹介してくれている。この投稿は専門的でありながら分かりやすく、とても楽しい。
やっぱり草花や山野草は大事にしたいものです。

 いよいよ春本番となる。
野山の花も咲きだし桜の芽も膨らも出してきているようだ。
私の家の周辺でも花が咲きだして、これからが楽しみです。
フクジュソウは今が真っ盛り、スイセンも咲きだした。レンギョウもかすかに膨らみだしたし、我が家の庭の山野草もいよいよ芽を出してくる頃である。
これには決して手を出されない。
なぜかというと、草取りと称して草むしりをすると、それがかみさんが大事にしていた山野草であることがこれまで何度あったことか。
その都度きついおしかりを受けており、今度こそは絶対そうしたものには手を出さないようにしようと思うのだが、ついつい手を出してしまう。
山野草は一見して雑草と変わらないように見えるが、一旦咲くとそれはそれはとても可憐な花をつける。
ごく一般的な花であっても、その花の名もよく知らない私にとっては、本当に見分けが付けにくいのである。
ましてや山野草となるとますますわからない、毎年河北新報の金曜日夕刊では「栗駒便り」で栗駒山の山野草を村のH氏が紹介しているし、毎日新聞では湯沢の方が草花を紹介している、フエースブックでは、湯沢市役所OBのS氏が丁寧に折々の草花を紹介してくれている。この投稿は専門的でありながら分かりやすく、とても楽しい。
やっぱり草花や山野草は大事にしたいものです。
いよいよ春本番となる。
野山の花も咲きだし桜の芽も膨らも出してきているようだ。
私の家の周辺でも花が咲きだして、これからが楽しみです。
フクジュソウは今が真っ盛り、スイセンも咲きだした。レンギョウもかすかに膨らみだしたし、我が家の庭の山野草もいよいよ芽を出してくる頃である。
これには決して手を出されない。
なぜかというと、草取りと称して草むしりをすると、それがかみさんが大事にしていた山野草であることがこれまで何度あったことか。
その都度きついおしかりを受けており、今度こそは絶対そうしたものには手を出さないようにしようと思うのだが、ついつい手を出してしまう。
山野草は一見して雑草と変わらないように見えるが、一旦咲くとそれはそれはとても可憐な花をつける。
ごく一般的な花であっても、その花の名もよく知らない私にとっては、本当に見分けが付けにくいのである。
ましてや山野草となるとますますわからない、毎年河北新報の金曜日夕刊では「栗駒便り」で栗駒山の山野草を村のH氏が紹介しているし、毎日新聞では湯沢の方が草花を紹介している、フエースブックでは、湯沢市役所OBのS氏が丁寧に折々の草花を紹介してくれている。この投稿は専門的でありながら分かりやすく、とても楽しい。
やっぱり草花や山野草は大事にしたいものです。